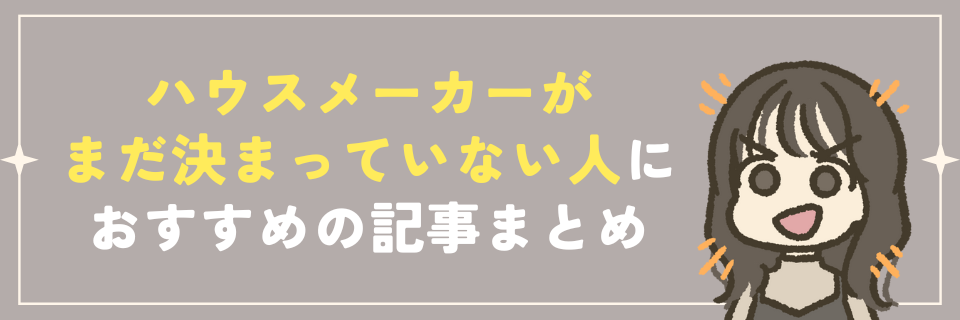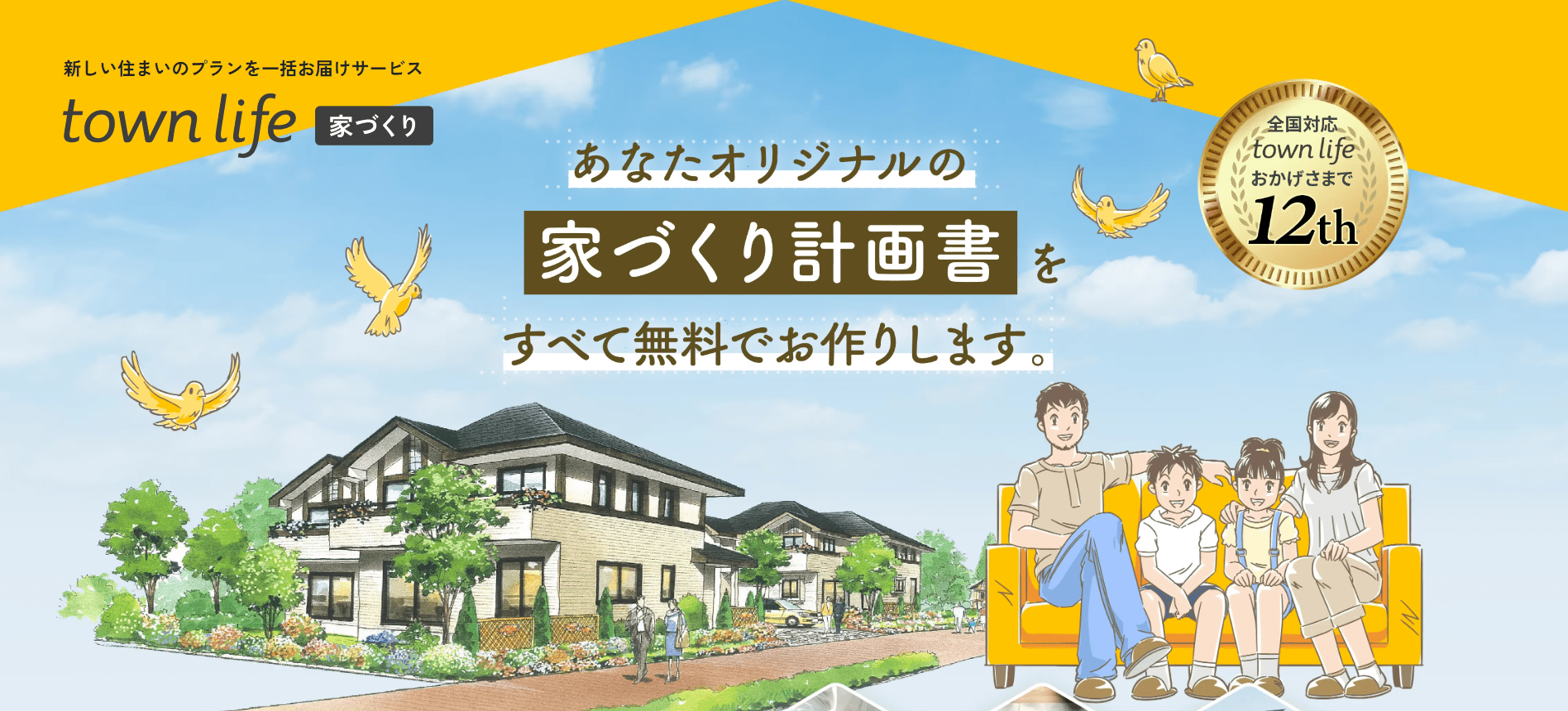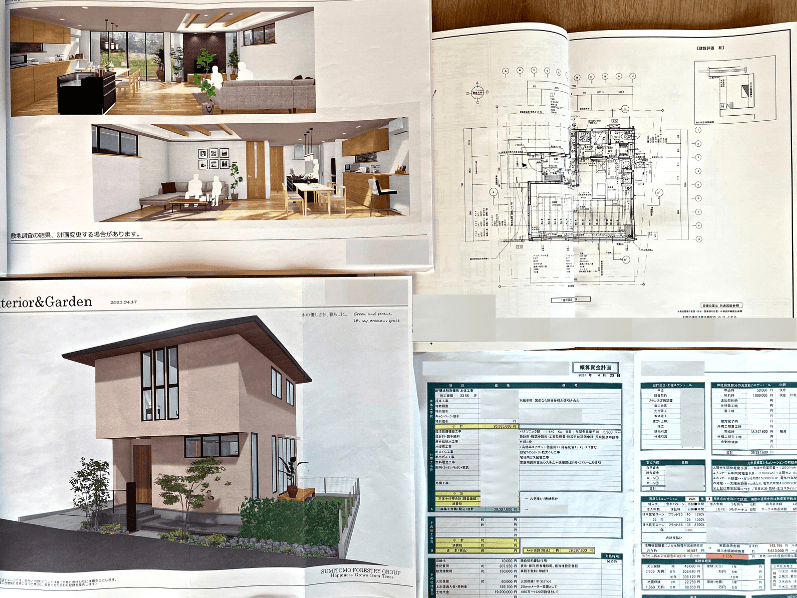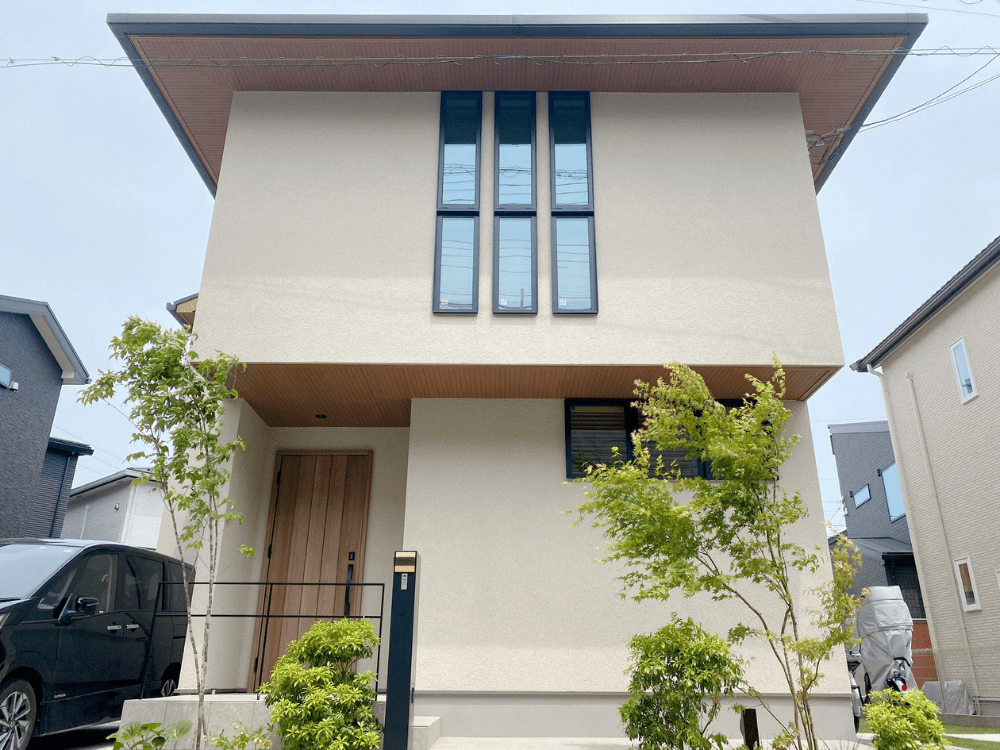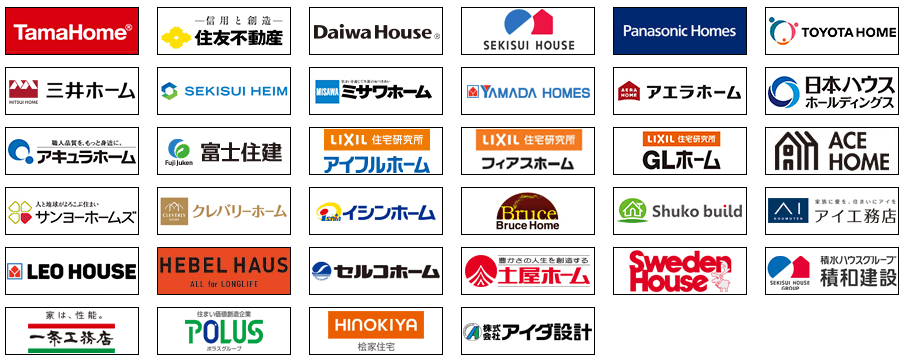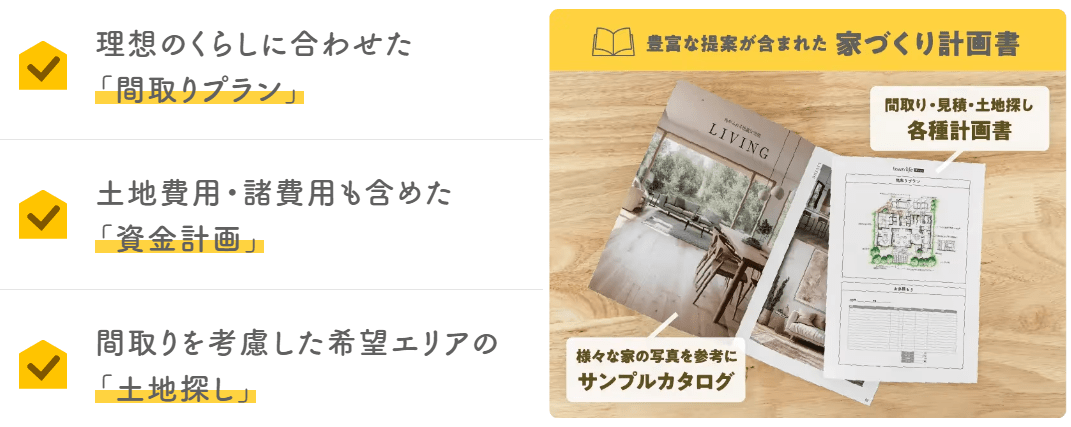- 電気ヒーターと温水循環式はどんな違いがあるの?
- どっちが人気でおすすめなのか知りたい!
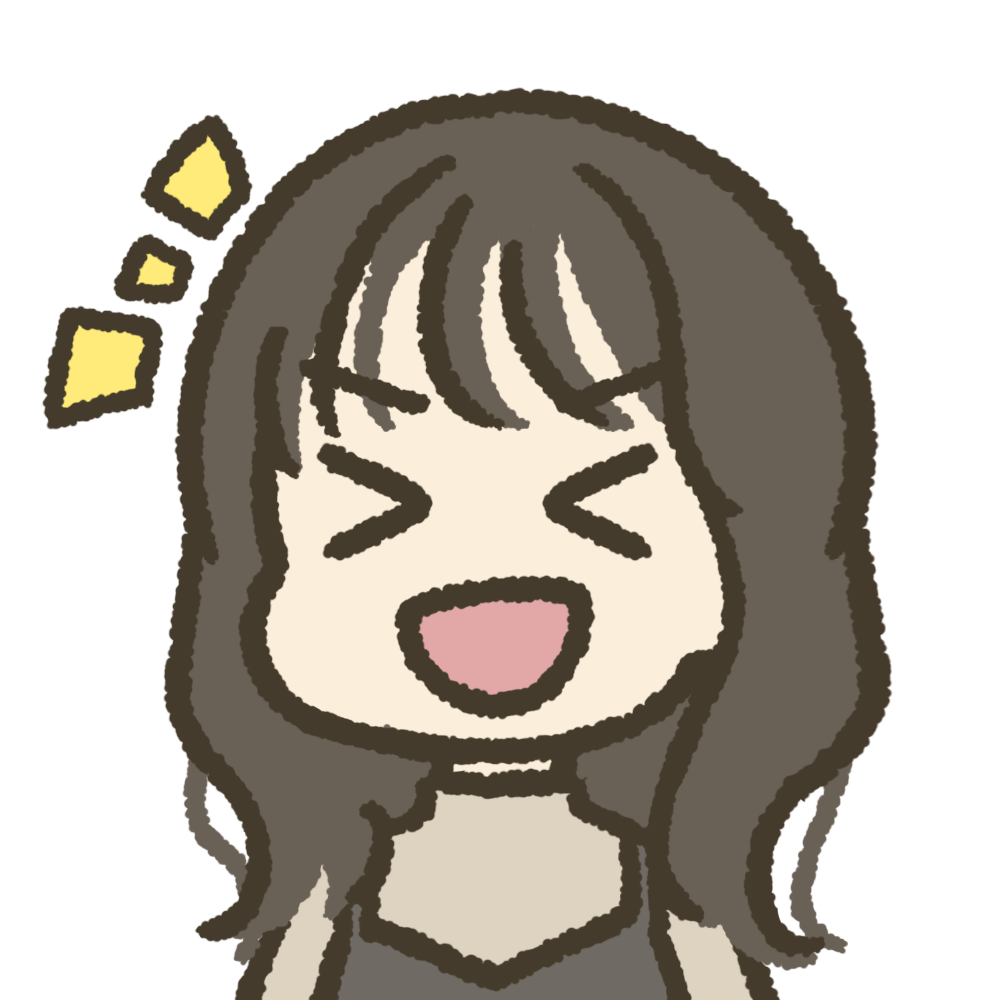
床暖房には種類があることをご存じでしょうか?
電気ヒーター式と温水循環式があり、熱源や仕組みからして大きな違いがあります。

生活スタイルや暖房器具の使い方によって選ばないと、採用してから後悔することもあります。
今回は、床暖房の電気ヒーター式と温水循環式を徹底比較します。
【床暖房】電気ヒーター式と温水循環式の違い
そもそも電気ヒーター式と温水循環式はどのような仕組みの違いがあるのでしょうか。
まずは、熱源の差があります。
電気ヒーター式の熱源:電気
温水循環式の熱源:ガス、電気、灯油
温水循環式は熱源を色々選べますがガスまたは電気を選択している人が多く、灯油を選ぶ人はほとんどいません。
また、機器の暖め方にも違いがあります。
電気ヒーター式:電気の力で床下に敷いてあるヒーターそのものが熱くなり床を温める
温水循環式:熱源で温めた温水を、床下に張り巡らされているパイプの中に循環させて床を温める
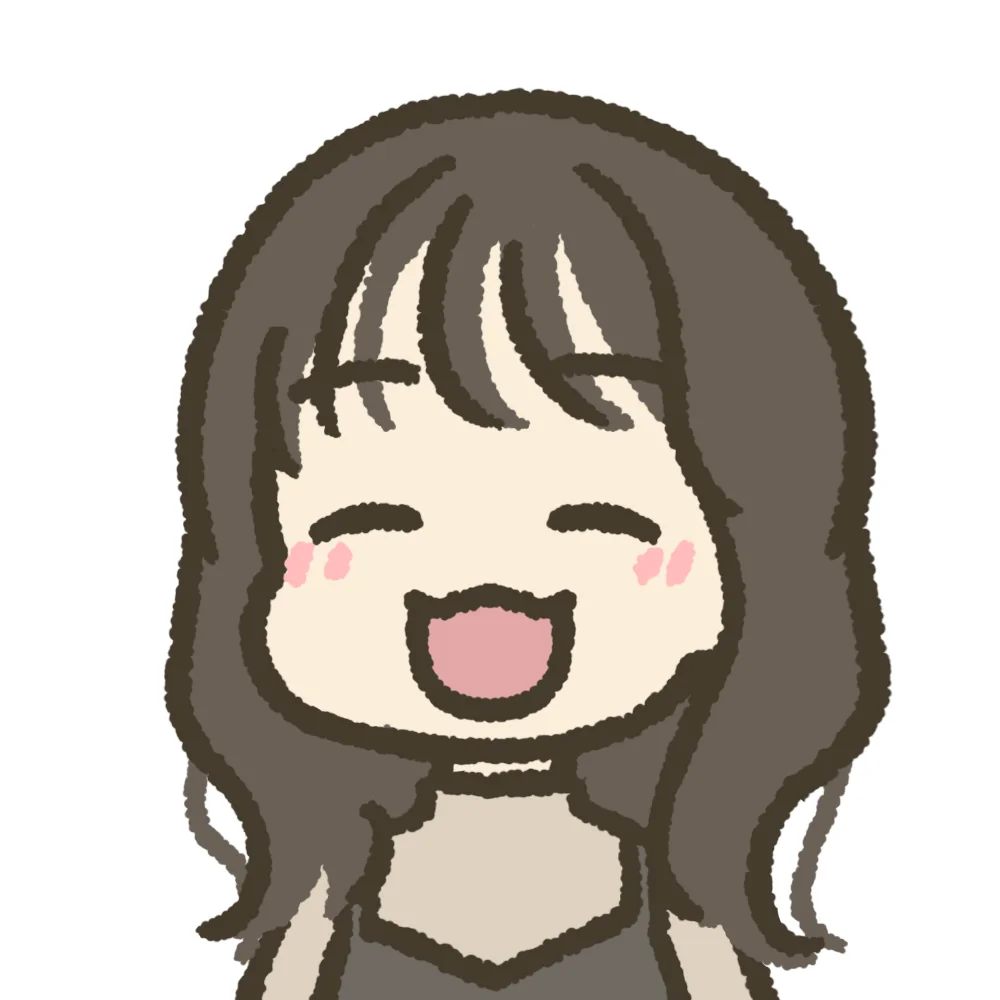
ではそれぞれの仕組みが分かったところで、様々な項目を比較してみましょう!
比較①導入費用
まず初めに導入するときにかかる初期費用です。
様々なメーカーの10畳用の定価をお伝えします。
すべて材料費のみの価格です。
| メーカー(商品名) | 価格 | |
| 電気ヒーター式 | Panasonic(フリーほっと)
※PTCヒーター |
696,100円(税抜) |
| LIXIL(HOTひといき)
※PTCヒーター |
708,200円(税抜) | |
| ツツミ(ツツミダンデー)
※PTCヒーター |
569,020円(税抜)
※床材を含まない |
|
| 温水循環式 | Panasonic(フリーほっと温水)
※ヒートポンプ |
407,300円(税抜) |
| リンナイ(床ほっとE)
※ガス |
194,000円(税抜)
※床材を含まない |
|
| DAIKIN(ホッとエコフロア)
※ヒートポンプ |
173,800円(税抜)
※床材を含まない |
電気ヒーター式と温水循環式は10畳用で約30万円の差がありました。
ただし、温水循環式は熱源となるヒートポンプや床暖房対応の給湯器を購入することが必須です。
すると、30万円という金額差は埋まってしまうか、逆転するケースも多いでしょう。
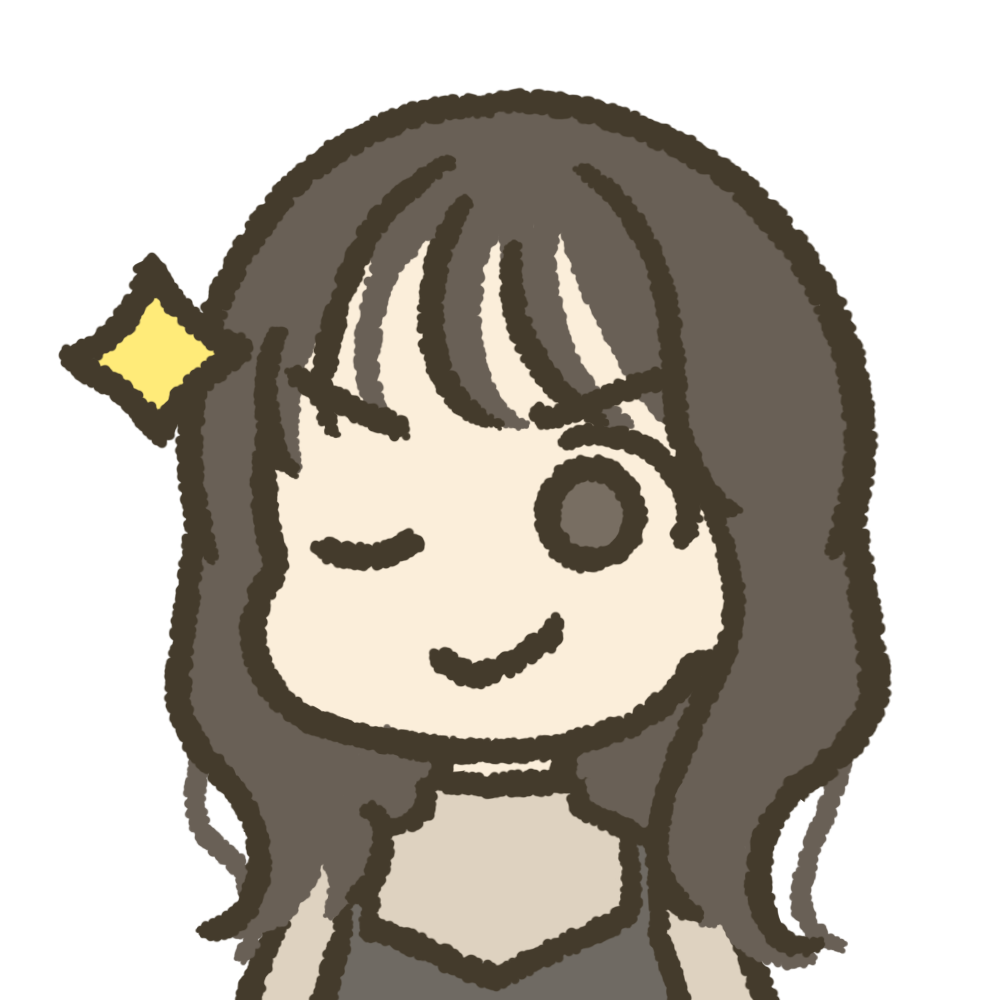
温水循環式は必ずヒートポンプ等を購入しなければならないと考えると、少ない面積であれば電気ヒーター式、広い面積であれば温水循環式がお得になるということがわかります。
比較②ランニングコスト
続いてランニングコストについても比較します。
すべて1日8時間使用した場合の光熱費です。
| メーカー(商品名) | 1ヵ月あたりの光熱費
(床暖房のみ) |
|
| 電気ヒーター式 | Panasonic(フリーほっと)
※PTCヒーター |
3,300円~7,300円(10畳) |
| LIXIL(HOTひといき)
※PTCヒーター |
4,500円(8畳) | |
| ツツミ(ツツミダンデー)
※PTCヒーター |
8,690円(10畳) | |
| 温水循環式 | Panasonic(フリーほっと温水)
※ヒートポンプ式 |
3,900円(10畳) |
| 東京ガス(NOOK)
※ガス |
3,210円(8畳) | |
| ノーリツ(MD-XE、MD-XD)
※ガス |
4,770円(8畳) |
トータル的に見ると、温水循環式の方がランニングコストは抑えられることがわかります。
もちろん、温度設定や外気温、ガス・電気料金によって試算結果は大きく変わりますので目安として参照してください。
比較③暖まり始めるまでの時間
床暖房はエアコンなどと比べて、暖まり始めるまでに時間がかかる暖房器具です。
電気ヒーター式と温水循環式でも立ち上がりの時間に差は出るのでしょうか。
| メーカー(商品名) | 時間 | |
| 電気ヒーター式 | LIXIL(HOTひといき)
※PTCヒーター |
30分
(床表面温度が10度から25度になるまでの時間) |
| ツツミ(ツツミダンデー)
※PTCヒーター |
10分
(床面が暖まり始める時間) |
|
| 温水循環式 | ノーリツ(MD-XE、MD-XD)
※ガス |
19分
(床表面温度が9度から27度になるまでの時間) |
| リンナイ(床ほっとE)
※ガス |
45分
(外気温5℃、室温が13℃から20℃になるまでの時間) |
一般的には電気ヒーター式の方が床面が早く暖まり始めると言われています。
ただし今回のリサーチでは、各メーカーでシミュレーションの温度も違い、床面・室内の温度の違いもありましたので、一概にどちらが良いとは判断できませんでした。
比較④メンテナンス
メンテナンスについても比較します。
電気ヒーター式:メンテナンスなし
温水循環式:不凍液を循環させる場合は交換が必要
基本的にはどちらもメンテナンスは必要ありません。
ただし、温水循環式を寒冷地で採用する場合は、水ではなく不凍液を入れるケースが多いです。
すると、10年に1回ほどの交換が必要になります。
比較⑤耐久年数
耐久年数はどちらも30年以上と言われています。
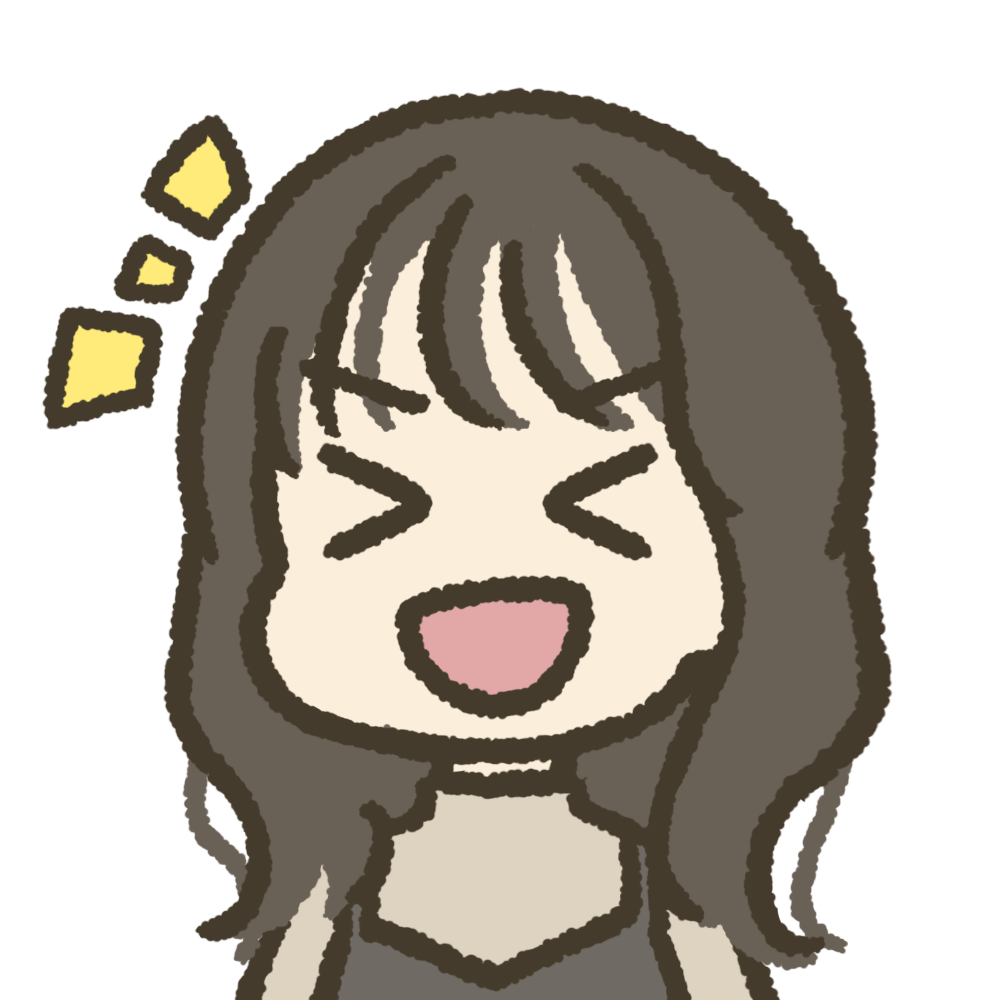
ただし、温水循環式は床暖房のシステムの他に、エコジョーズやエコキュートなどの熱源機の耐久性も考慮しなければなりません。
これらの耐用年数は10年程度と言われています。
温水循環式を採用する場合は、熱源機の買い替え費用も頭に入れておきましょう。
比較⑥音
稼働させたときの音についても比べてみます。
電気ヒーター式:ほとんど音は気にならない
温水循環式:室外機の音が気になることがある
温水循環式は屋外にヒートポンプを置くため、室外機の音が気になるという意見があります。
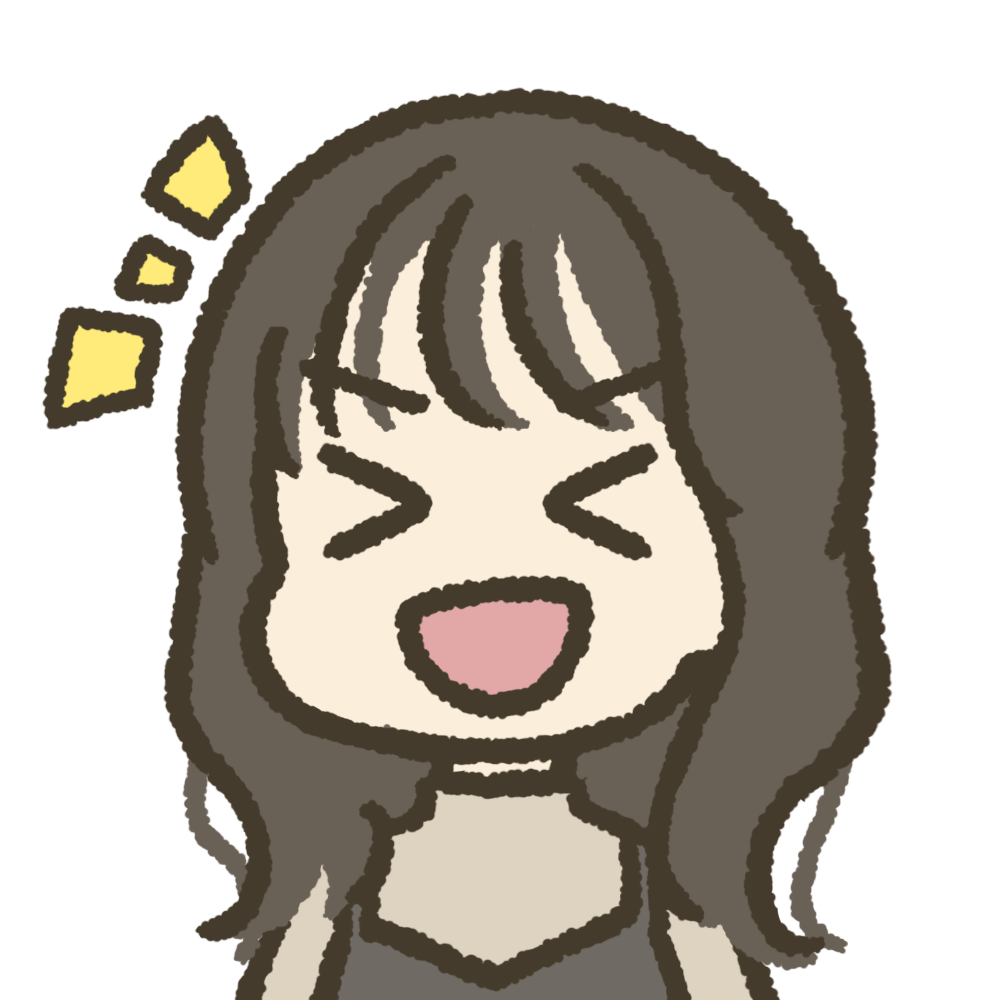
室外機の設置場所に気を配るといいでしょう。
比較⑦安全性
続いて安全性についてです。
床暖房は高温になることがないので、ストーブなどと比べて安全性が高いと言われています。
電気ヒーター式と温水循環式で安全性の違いはあるのでしょうか。
結論から言うと、どちらのタイプでも低温やけどを起こす危険性はあります。
床暖房に長時間触れていると床と人・物の間に熱が溜まるからです。

ただし、温水循環式は温水は40度前後で管理されていますので、電気ヒーター式と比べて床の温度が上がりにくいです。
そのため、一般的には温水循環式の方が安全性が高いと言われていますが、全く危険性がないわけではないので誤認しないようにしましょう。
それで、結局どっちが良いの?
では、結局どちらが良いのでしょうか。
個人的には、温水循環式床暖房をおすすめします。
理由は次の2つです。
- 自分自身が家にいる時間が長いこと
- 広範囲に施工したい
私は家にいる時間が長いため、床暖房を稼働させている時間も長いです。
そのため、ランニングコストが抑えられる温水循環式を選びました。
また、限られた空間だけでなく広範囲で施工をすることも踏まえて温水循環式にしました。
温水循環式は広範囲に施工するほど、初期費用のお得さを感じられるからです。
広範囲に施工したいと思ったのは、冬場は床暖房だけで過ごしたいからという理由です。
一般的に床面積に対する床暖房の施工面積が70%を超えていれば、床暖房だけでも暖房器具として機能すると言われています。
エアコンの風が嫌いな私は、広範囲で施工して床暖だけで過ごすという選択をします。
以上のことから温水循環式を選びました。
もちろん施工範囲や稼働時間などによって電気ヒーター式が向いている人もいます。
自分にとってメリットの大きい方を選択しましょう。
採用率が高いのは?主流はどっち?
実際に選ばれているのはどちらなのでしょうか?
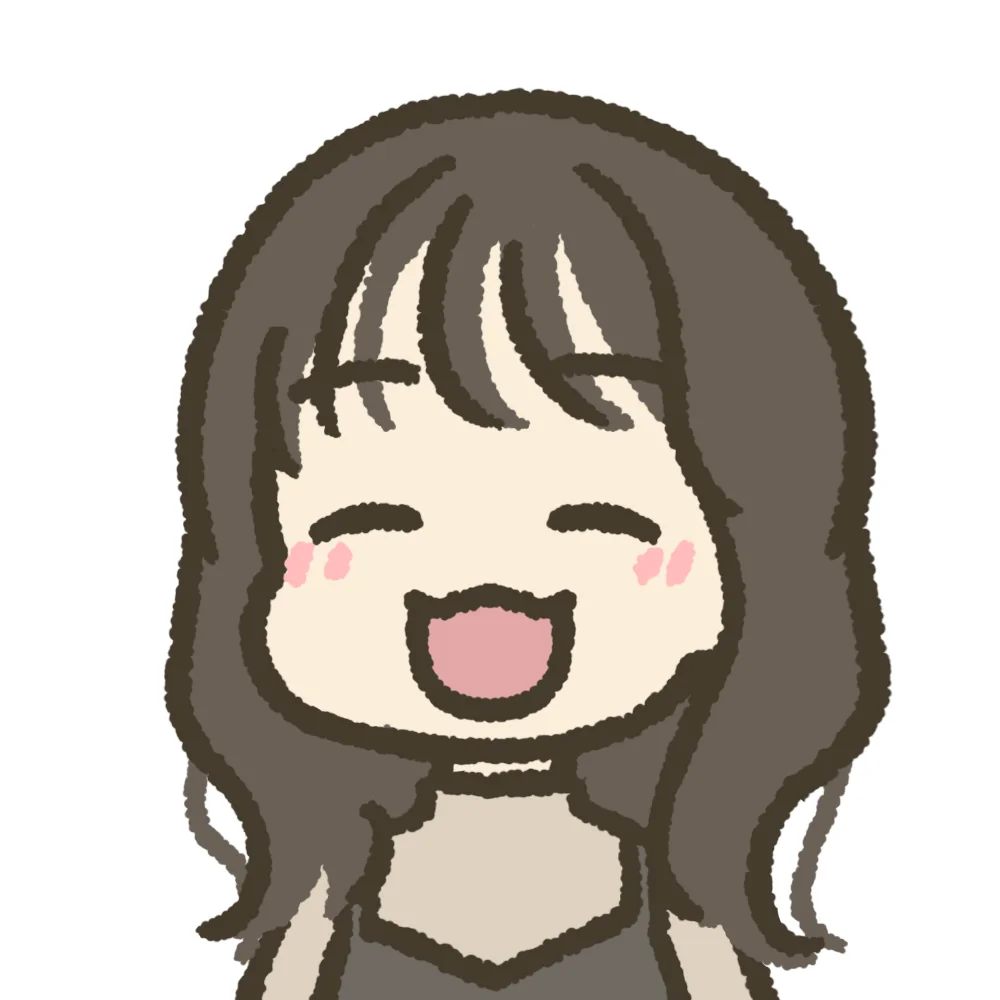
電気ヒーター式よりも温水式の方が大手の取扱メーカーが多いです。
名前を聞いたことのない会社の電気ヒーター式を選ぶより、大手の温水循環式の安心感で選ぶという方もいます。
また、多くの方が部分的に施工するというよりは、LDK全体などの広範囲に施工したいと考えるので温水循環式が選ばれています。
電気・ガスの選択肢があるという点も理由の1つかもしれません。
自分に合った床暖房を選んで快適な冬を過ごそう
電気ヒーター式と温水循環式の違いについてまとめます。
| 導入費用 |
|
| ランニングコスト |
|
| 暖まり始めるまでの時間 |
|
| メンテナンス |
|
| 耐久年数 |
|
| 音 |
|
| 安全性 |
|
どちらも良し悪しはあり、生活スタイルによっておすすめの床暖房は変わってきます。
他の暖房器具と比べ、買い替えが安易ではないので慎重に検討して選びましょう。